社会は今、多様性や寛容性を求めています。
その要請に建築家はいかに応えようとしているのか。
作品を通して探ります。
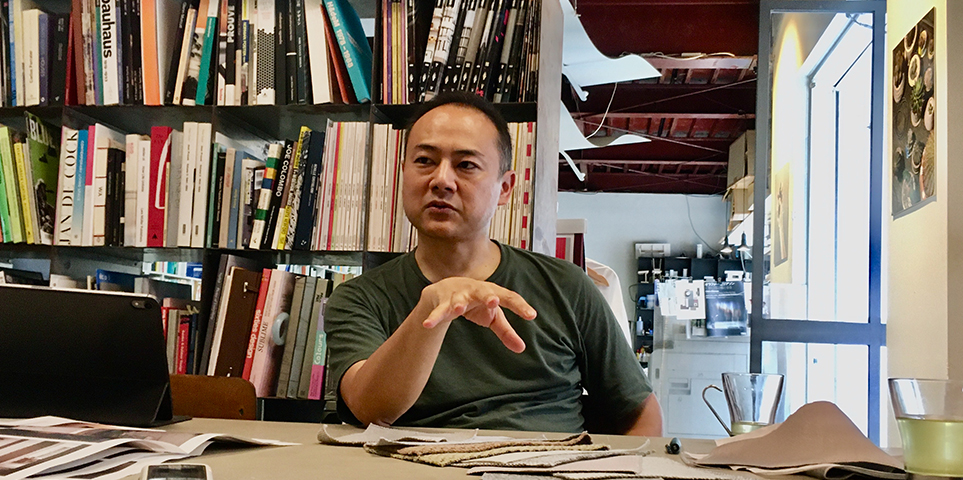
第27話
家具づくりから考える建築空間
芦沢啓治|芦沢啓治建築設計事務所
2020.09.07
「空間に対する明確なコンセプトが込められていれば、家具が住空間を変えていくこともありうる」と言う芦沢啓治氏。建築、インテリアから家具、照明のデザインまで幅広く活動する氏にお話をうかがった。
ホテルのプロジェクトが増えていますね。最新作や計画中のプロジェクトについてお聞かせください。
芦沢啓治(以下、芦沢):最初にホテルの仕事をしたのは、ナインアワーズ(9hours)というカプセルホテルで、2年前に蒲田店がオープンして先日名古屋店が完成、現在博多店のプロジェクトが進行中です。あと2つくらい担当する計画です。ナインアワーズは明確なブランドがあるので、それに対して僕たちが寄与できることは何か、あるいは平田晃久さんがやろうとしていること、成瀬・猪熊がやろうとしていることは何か、さらにはビジネスそのものに対して僕らができることは何か、考えながらやっていますね。
芦沢さんには何が求められているのですか?
芦沢:見栄えやこけおどしではなく、ある種のクオリティですかね。やはりホテルというのは人がある時間滞在する場所です。その滞在の質が結果的にビジネスをつくる、あるいはブランドを成長させていくことになるので、デザインもそうですし、空間の有り様のようなところまでクオリティが求められます。施主もこういう空間にしたいというアイデアをもっていますが、彼らはブランドに対してある程度柔軟に構えているところがあります。例えば全体の構成の中で機能的にプランニングすることです。できた余白みたいなものの使い方を僕たちが提案するといったこともしていて、そこはとてもやりがいがあります。

ナインアワーズ 名古屋駅 名古屋市中村区 2020年
写真:Nakasa&Partners
他にも計画中のホテルがありますか。
芦沢:一つはインテリアの仕事で都内に計画中のホテルですが、建築的な力が必要だということで、プロポーザルで選ばれました。また、レストランとラウンジスペースも僕たちがコントロールしています。もう一つもデザインホテルで、どちらも数年後完成することになっています。といっても設計は佳境で、ほぼもう動かないというところまで詰めています。
実は現在、ナインアワーズを含めホテルの仕事が事務所の活動の半分近くを占めています。近年のインバウンドブームでホテル関係の仕事をしている建築家は多かったと思いますが、いわゆる景気の後退が原因ではない、予測不可能な今回のコロナ災禍で、方向転換を考える人も多いと思います。僕自身は自分が選んでこういう仕事をしてきたので、選び方を考え直すことはあっても、路線は変える必要はないと思っています。自分たちの力が生かせるところでちゃんと仕事をしていけばいい。結果、ホテルの仕事がメインではなくなる可能性があります。
ホテル以外ではどういった仕事が多いのですか?
芦沢:住宅や計画段階ですが飲食店なども手掛けています。あとは家具の仕事ですね。自分で投資しながらやってきたことがここ2〜3年でビジネスになってきて、事務所の事業の一つとして確立されてきた。近所にショールーム兼ゲストハウスを設けて、家具を売っているわけではないのですがプロダクトデザインのスタッフが常駐しています。それくらいで、個人のお客さんは最近意図的に減らしてきています。
それはなぜですか?
芦沢:個人のお客さんの仕事は楽しいし得意なところでもあるのですが、スタッフが10人くらいになると、僕がそこに時間とエネルギーをとられてしまうと他の仕事に影響が出てしまう。
それと、個人邸は以前と比べ施工費などが上がってしまい、お受けするのが厳しい状況が続いています。そのためお断りするケースが結構ありますが、それでも年に1〜2件は今もやっています。
最近手掛けられた住宅を紹介いただけますか?
芦沢:去年竣工した「用賀の家」があります。5人家族ための延床面積約400㎡という住宅です。1階は駐車場、ジム、ゲストルーム、倉庫、2階は駐車場の上に中庭のように植栽を施し、その周りにリビング、ダイニング、キッチンとご主人の書斎、そして3階には子供部屋3つとマスターベッドルーム、バスルームという構成です。1階がRCで2、3階は木造ですが、1階は地下という設定で、木造2階建てという構成になっています。
住宅については、家具の仕事をしてきたこともあって、空間だけつくって後は勝手にどうぞということではなく、住宅の家具はどうあるべきか、かなり細かいところまで提案しています。

用賀の家 世田谷区 2019年
写真:Daici Ano
住宅の依頼はどのようなきっかけで入ってくるのですか?
芦沢:紹介が多いですね。また一回引き受けると、その後長い付き合いになる人もいます。住宅がきっかけでその方の会社のオフィスをデザインしたり、中には「別荘を考えている」「庭を広げたから小さな小屋を建てたい」というような話もあります。そうやって何度かお宅に足を運ぶうちに、そこでどういう生活をされているのか疑似体験させてもらえるし、パーティの時に人がどのように空間を使うかなど、いろいろ学びがありますね。
クライアントつながりで広がる仕事というのは他にもありますか?
芦沢:今カリモク家具さんと継続してお仕事をさせてもらっています。家具のデザインだけでなく工場オフィスの設計であったり、ショールームのデザインの仕事もあります。あるいは他のデザイナーと一緒にブランドを立ち上げていくときのディレクションとか、芋づる式に広がっていって、家具のデザインから空間、あるいは生活に対する考え方、捉え方を共有して展開する仕事になっているのはとても面白いですね。家具の仕事は、もしかするとアーキテクトよりよほど住環境を変えていく可能性をもっていると思います。要は住宅は1個しかできないが、家具はちゃんと売れれば何万個と売れる。その時その家具に空間に対する明確なコンセプトが込められていれば、それが住空間を変えていくことだってありうるわけです。
なるほど。
芦沢:そういう流れでいうと、パナソニックさんと一緒につくったテレビもそうです。これはテレビの位置が住宅の間取りを決定していないかという疑問からスタートしたプロジェクトです。例えばテレビを置いたらその前にコーヒーテーブルがあってソファがあって、その後ろにダイニングテーブル、キッチンがある、つまりテレビを置く位置からきれいに空間の配置が決まっていく。ところがテレビを見ている私たちの視線というのは、必ずしも見たい景色ではなかったりする。本来は空間としてはこう見てもらいたいというのに、なぜか隅っこの方を見続けることになっている。もしテレビにもっとフレキシビリティがあれば、あるいはもっと軽くてポータブルなものになれば、住宅は変わるのではないかということです。それをパナソニックさんと一緒に研究開発して、かなりリアルなプロトタイプ(コンセプトモデル "ONTV")をつくりました。2018年には都内の蔦屋家電にパナソニックが設けた新しいタイプのショールームに展示してお客さんの反応を見たのですが、評判は上々でした。実はその後担当が変わったこともあってまだ確定ではないのですが、一応当初の予定では2021年に商品化されることになっていました。

パナソニック”ONTV”コンセプトモデル 2016年〜
商品開発というのは5年くらいかかります。
芦沢:そうですね。僕がこのテレビの開発にかかわったのも2016年だったと思います。薄いとか大画面といったところで競っていると価格だけの競争になってしまう。だからもっと柔らかいところからスタートしてまったく違う着地点を見つけていくようなことをしないと、普遍性はもちえないのではないかと提案したのがこのテレビです。
そこで全体のデザインと機構部分をパナソニックさんと一緒に開発して、これでリビングが変わっていくようなプロダクトを目指しましたし、実際に変わると思います。
例えばテレビはまだまだ重いですよね。さらに付随するものがいろいろある。でも電源以外は今は全部無線で飛ばせますからコード類は電源だけにして掃除機のような仕様にしています。パナソニックさんも開発にかなりの投資をしてくれて、当初20㎏あったモニターが10㎏切るくらいまで軽量化できました。
ただ、できたのはいいのですが、問題はどこで売るかということ。一般にどこでテレビを買うかというと量販店が多いのですが、量販店は多種多様なテレビを並べて置いてあるだけで、リビングを考えた上で展示されているわけではない。でも本来は適正な大きさがあるはずだし、リビングとテレビの関係性を考えたショップがあってもいいはずです。つまり量販店を基準に考えている以上、そんな話は出てこないし説明もできない。じゃあ家具屋さんに置いてもらえばいいかというと、そういうことができる立派で素敵な家具屋さんが日本にいくつあるか。そこで商品化の話が前に進まなくなるわけです。売り方の問題から見えるのは、いわゆる家電製品と僕たちの生活が乖離してまったく別に動いているということです。
本来ならアーキテクトはこのようなテレビであったり生活家電に仕事として入り込む余地がたくさんあって、目の前のモノの良し悪しだけではなく、俯瞰して見て教えて欲しいというニーズはあるはずです。それをきちんと論証してデザインしていくというのは実は結構スキルが必要です。たまたま僕はそういうことを一所懸命やってきた結果仕事という形になってきたのだと思います。狙ってやったわけではないのです。
家具で具体的に紹介していただけるものはありますか?
芦沢:例えば「石巻工房」は約10年前にスタートして、今6人くらいの会社になっていますが、基本は石巻で生産し販売することで、企業としては回っています。最近「メイド・イン・ローカル」というプロジェクトをスタートさせ、家具を気に入ってくれた海外のブランド等が、僕たちがデザインした家具を現地で製作し現地で売るという活動をしています。現在契約を結んでいるのはアメリカ・デトロイト、ドイツ・ベルリン、イギリス・ロンドン、フィリピン・マニラで、それぞれ現地で手に入る材料で現地で製作して現地で販売します。いろいろな意味でとても面白いプロジェクトです。というのも、こういう時代ですから消費者もそれがどういったエコロジーの循環の中でつくられているものなのか聞いてくる。
中国で大量に安くつくったものにブランド力をつけて売っていますというのではなかなか消費者を納得させることができなくなっている。世界中がそういう方向に意識が向いているわけです。それから実はカリモクさんにも石巻工房の家具をつくってもらっていて、それは6人の会社では300人のオフィスに対応できないけど2000人規模のカリモクさんなら可能です。ただ石巻工房と組むからには、僕たちが始めたときのある種のパブリック精神を込めながら、新たなストーリーを共につくるというプロジェクトとして、皆さんに取り組んでもらっています。

石巻工房の新プロジェクト「メイド・イン・ローカル」
ベルリンのパートナー企業はHLZFR.GmbH
写真提供:HLZFR.GmbH
なるほど。
芦沢:家具の仕事は家具デザインだけじゃない面白さがあります。例えば空間との関係性からソファはどうするか、その張り地は何にするか、それと組み合わせてカーテンは何を選ぶか、コストも念頭に置きながらそういうところまで気配りできる設計者はなかなかいない。じゃあ家具メーカー側がそういうことに対して目利きかというとそうでもない。結局上手にコラボレーションする必要があります。双方にとって。そういうことが家具づくりを延々とやっていくうちにわかってきた。それが空間のクオリティに如実に現れてきます。結果的にホテルの仕事にもつながってきたのだと思っています。
ガラスという素材について、どのようにお考えですか?
芦沢:ガラスにはまだまだ魅力がありますね。最近発表した家具コレクションの中にもカラーガラスを使ったテーブルがあります。このテーブルでは、ガラスをマテリアルとして扱える感じがあって、僕は気にいっています。
その最新の家具コレクションとは?
芦沢:カリモクさんから発表されたKarimoku Case Study(カリモクケーススタディ)という新ブランドで、特定の建築プロジェクトで得たインスピレーションから家具をデザインするというのがコンセプトです。第一回コレクションは都内のテラスハウスのリノベーションをデンマークの設計事務所ノーム・アーキテクツとともに手がけたことから生まれたコレクションです。作品は昨年コペンハーゲンで開催された展覧会で初披露し、その後六本木アクシスで新ブランドとして正式発表しましたが、今世界各地にいる僕たちのパートナーが扱ってくれるまでになっています。そのノーム・アーキテクツは大変ユニークな設計事務所で、カリモクケーススタディ以外でも、一緒にレストランやホテルを設計したりしています。彼らは、建築、インテリアに加えて家具デザインもするしブランディングも手掛けるなど、一緒に仕事をするといろいろと学びがあります。

砧テラス(リノベーション) 世田谷区 2019年
設計:芦沢啓治建築設計事務所+Norm Architects
家具:カリモクケーススタディ
写真:Jonas Bjerre-Poulse
飲食系の家具で進行中のプロジェクトはありますか?
芦沢:ブルーボトルコーヒーの新店舗「BLUE BOTTLE COFFEE みなとみらい」で、場所が横浜美術館の前の路面店です。面白いのが外部空間を横浜市が使っていいと許可してくれたことで、ベンチのデザインまでさせてもらいました。そこには白い彫刻がたくさん並んでいて、それに寄生するかのようなベンチを考えました。どういうことかというと、その彫刻のそばにベンチを置くと、彫刻の上にコーヒーカップが置ける、あるいは逆に彫刻に座ればベンチがテーブルになるようなデザインです。店舗内はほとんどがオリジナルで、先ほどのカリモクケーススタディのコレクションの家具も使っています。つまり僕とノーム・アーキテクツのデザインで、僕たちとしては空間から家具をつくるというところから始めたブランドでしたが、ここでは逆にそれをインテリアに活かし、かつ呼応させて空間をつくったという感じです。照明も含め家具をほぼ完璧にコントロールしていて、そういう意味では単にインテリアデザインをしましたというだけじゃない。一見すると普通に見えるかもしれませんが、かなり特殊なことを、しかも地味なレベルでやっています。
事務所をどのようにしていきたいですか?
芦沢:ローカルアーキテクトをやった経験もあり、世界中のアーキテクトやデザイナーと仕事をしてきました。その経験からどこの国に行ってもプロフェッショナルとしてきちんと通用するチームでありたいと思っています。そのために変えていかないといけないのは、本当の意味での働き方です。日本の設計事務所にいまだに蔓延する「がむしゃらに」とか「手取り8万円でも」といった古い体質はやめないと永続しないし、インターナショナルに良い人材を採ろうと思えば絶対に不可能です。恥ずかしいですよね。おそらくいずれ改善されていくはずですが、私の事務所としては今は投資と思ってそういった状況を変えようと考えています。
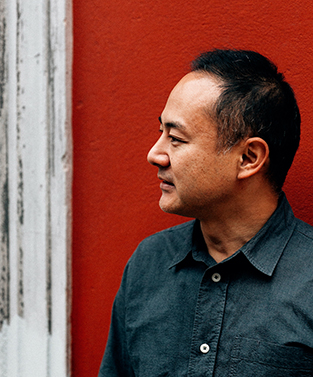
インタビュアー
