
今回から数回にわたって、『遮音と窓ガラス』について解説いたします。
よく、「音はむずかしい」という声を聞きますが、“できるだけ分かりやすく”を心がけていきますので、
お付き合い下さい。まずは、「音」に関する基本編です。
- ●音ってなに?
- 私達が耳にする音の正体は、空気の振動です。例えば、太鼓をたたくと皮が振動し、
皮の付近の空気が同じように振動して、空中で広がって耳に届いた時に、音として感じます。
従って、空気の無いところには、音は存在しません(ちなみに、宇宙は真空なので無音です。
“スター・ウォーズ”などのSF 映画では、戦闘機の爆発音が聴こえていた気がしますが…
娯楽ですからね)。 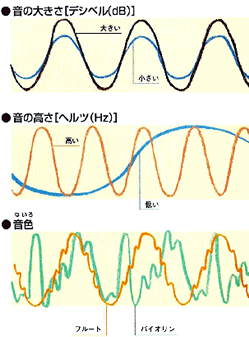 ●音を表す単位(音の3要素)
●音を表す単位(音の3要素)-
- 音の大きさ(dB)
音は、空気振動が大きいほど強く、
小さいほど弱くなります。
このエネルギーを示す物理量の単位が
デシベル(dB)です。
- 音の高さ(Hz)
空気の波が、1秒間に振動する回数が
多いほど高い音となり、少ないほど
低い音になります。
これを周波数といい、
ヘルツ(Hz)で表します。
500Hz とは、1 秒間に500回振動する
音の事です。 - 音色
さまざまな音色があるのは、
波形の違いにより生まれるのです。身近なところで、NTT(117)の時報の周波数は…
・ 1秒ごとの時報(ピッ、ピッ、ピッ…) 2000Hz
・ 10秒ごとの時報(ポーン) 1000Hz
・ 30秒ごとのカウント音(ポーッ、ポーッ、ポーッ) 500Hz - 音の大きさ(dB)
- ●騒音とは?
- 一般的に、不必要な音、不快な音、邪魔な音、好ましくない音のことを“騒音”といいます。
航空機、電車・列車、自動車、工場、建設作業、音楽や近隣などの生活などが、
騒音になる要素を含んでいます。
騒音の大きさは、騒音レベルと呼ばれ、デシベル(dB)で表しますが、以前に「ホン」や「dB(A)」と
表現・表記してきた騒音レベルも、現在は全て「デシベル(dB)」で表すこととされています。
そのほか、音は、温度や風の影響も受けます。昼間よりも夜間の方が聞こえやすくなったり、
風上よりも風下が聞こえやすいのは、この性質によります。
また、音源からの距離が遠いほど、音は小さく聞こえます。これを距離減衰といいます。
常日頃、耳にしている音ですが、このように、なかなか奥深い現象であることが分かります。
(次号へ続く)
