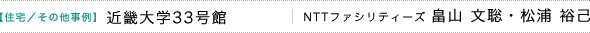

日本初となる建築学部新設に伴う既存学舎のリニューアルにあたって、私たちがまず考えたのは、そこで過ごす人を主役とした空間づくり、そこでの行為がさまざまなコミュニケーションを誘発する環境づくりということです。そこでは建築やインテリアはデザイン表現としてではなく、それらを浮かび上がらせるプラットフォーム、つまり背景として現れることになります。
“学ぶ”という行為の本質が、教授から学生への一方的な情報伝達ではなく、多様な個性が刺激し合うインタラクティブなコミュニケーションにあるとすれば、それを体現した空間こそがいま求められているのであり、そうした学舎のあり方は、構造や設備、土木のみならず、芸術や社会学、人間工学など種々の学際分野とのコラボレーションによってひとつの環境をつくり出す『建築学部』にふさわしいのではないかと考えたのです。
そこで、上階の研究室の壁をガラス張りにし、内部での活動を共用スペースへとにじみ出させるとともに、院生室を各フロア毎にひとまとめにすることで、異なる専門分野を持つ学生たちが刺激をし合い、ときには協力し合いながら共通の課題に向き合える環境を用意しました。
また、そうした状況を学舎内のみならずキャンパスへと波及させるために、建物のエントランスもガラス張りとし、そこにギャラリーやワークショップスペースなど、学舎内での活動を社会化するための半オープンな場を設えました。それにより、学舎とキャンパス、建築学部の学生と他学部の学生とを緩やかに連結することを考えたのです。
前述の通り、このエントランス空間での主役も、ここを行き交う人々であり、ここでなされる行為です。デザインが主張しないことはもちろん、照明や素材をはじめとするすべてのディテールは、そこでのコミュニケーションを浮かび上がらせるために機能しなければなりません。
そうした中で、空間構成のメインエレメントである壁材の機能として私たちが着目したのは、映り込みによる多層性の獲得です。映り込みという事象は、そこで行われている行為を増幅させることでさまざまなコミュニケーションを誘発させるという目的に対しての直喩的、隠喩的表現を併せ持つ。
そのときに、主役である行為を妨げることなく、なおかつそれを際立たせるためには、たとえばステンレス鏡面やミラーによる鮮やかな反射ではなく、主従が明確となる微妙な映り込みが望ましい。それに適う素材がカラーガラスのラコベルでした。
カラーガラスは、その素材としての存在感もまた大きな魅力です。ラコベルは主張しすぎない静ひつ感と美しい奥行き感を両立する素材であり、それ故、強さを持つ素材です。何も装飾を施していないミニマルな空間でも、ファサードのレンガタイルによる様式的なデザインにも負けない豊かな存在感を獲得することができた。カラーガラスは、背景としての空間を具現化するニュートラルさと、素材としての存在感を両立することができる希有な素材です。
壁材としてのカラーガラスが生み出すニュートラルなプラットフォームで、どのようなコミュニケーションが誘発されるのか。
そして、その結果、ここで学んだ学生たちが将来どのような空間を生み出していくのか、その成果が現れることをとても楽しみにしています。




『ラコベル』 ピュアホワイト

1980年生まれ。2004年九州大学工学部
建築学科大学院卒。NTTファシリティーズ関西事業本部建築デザイン室。